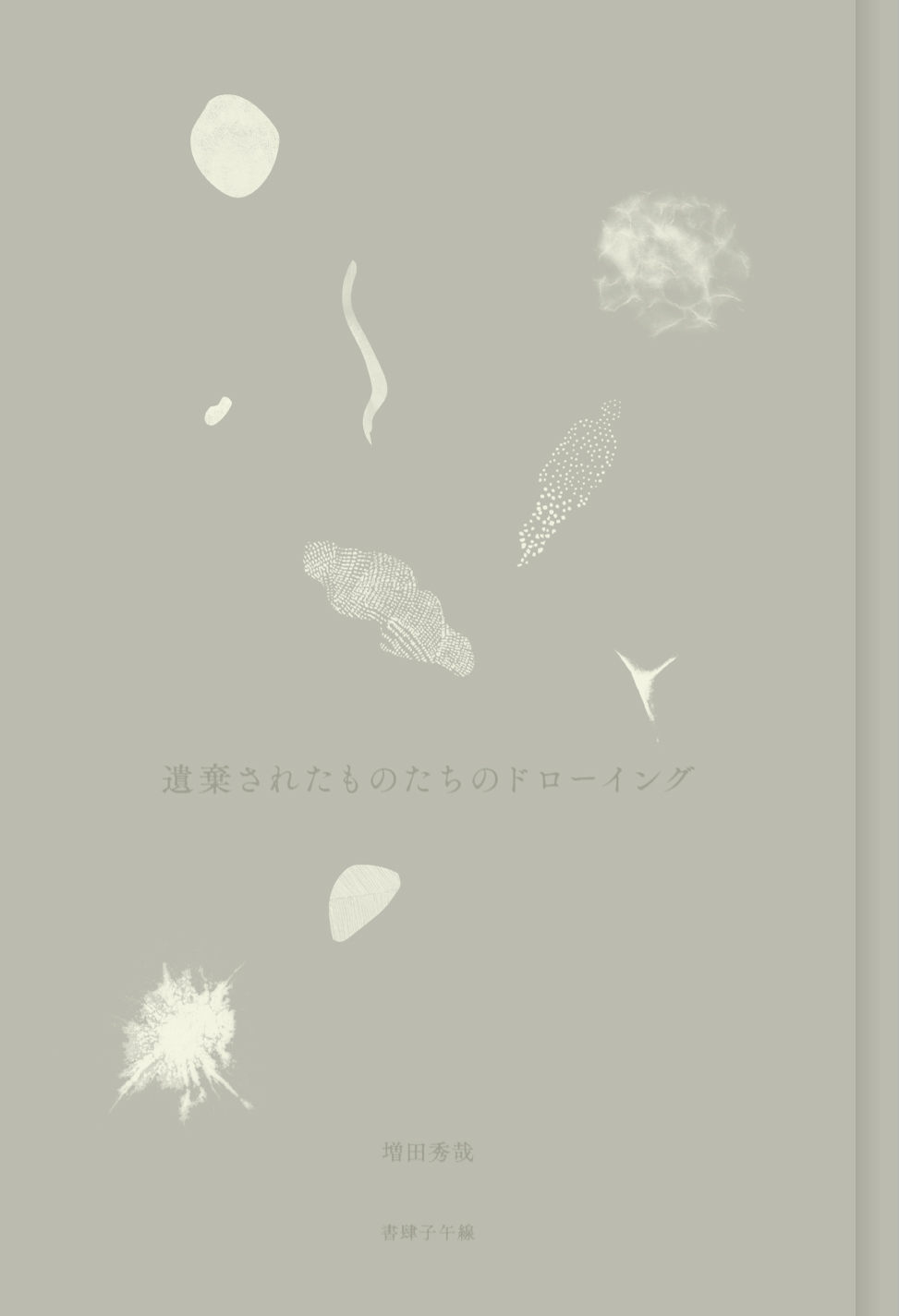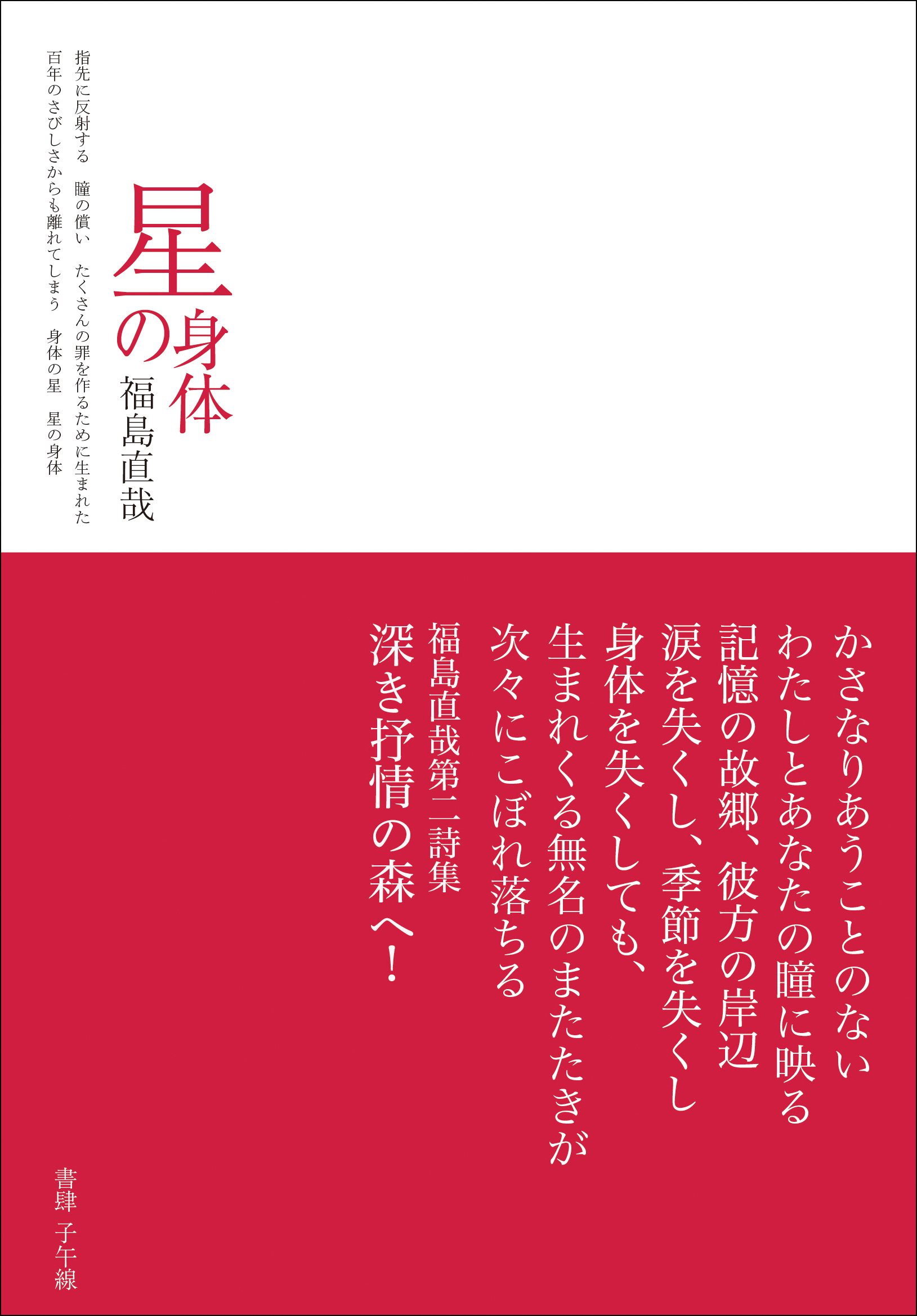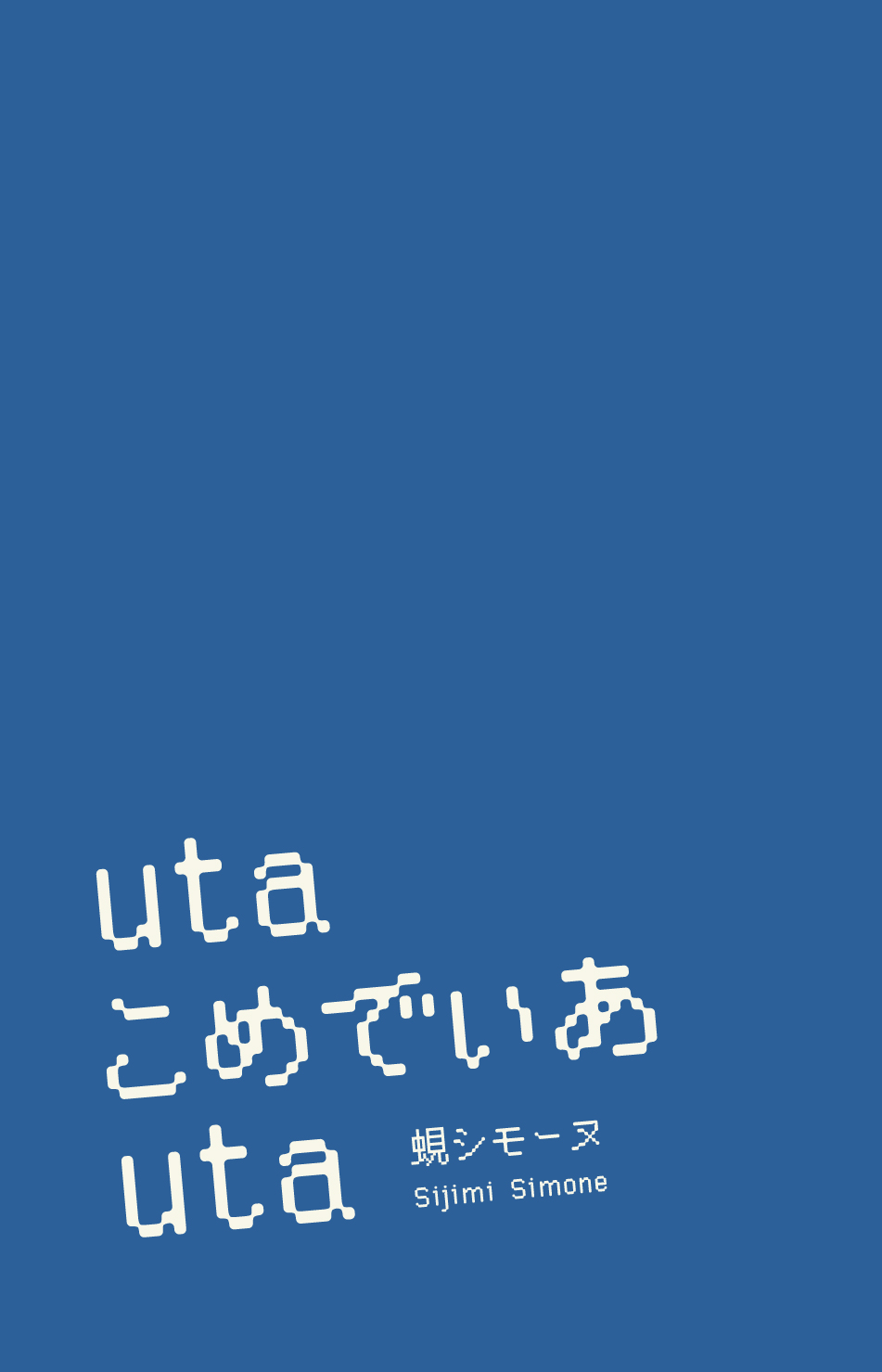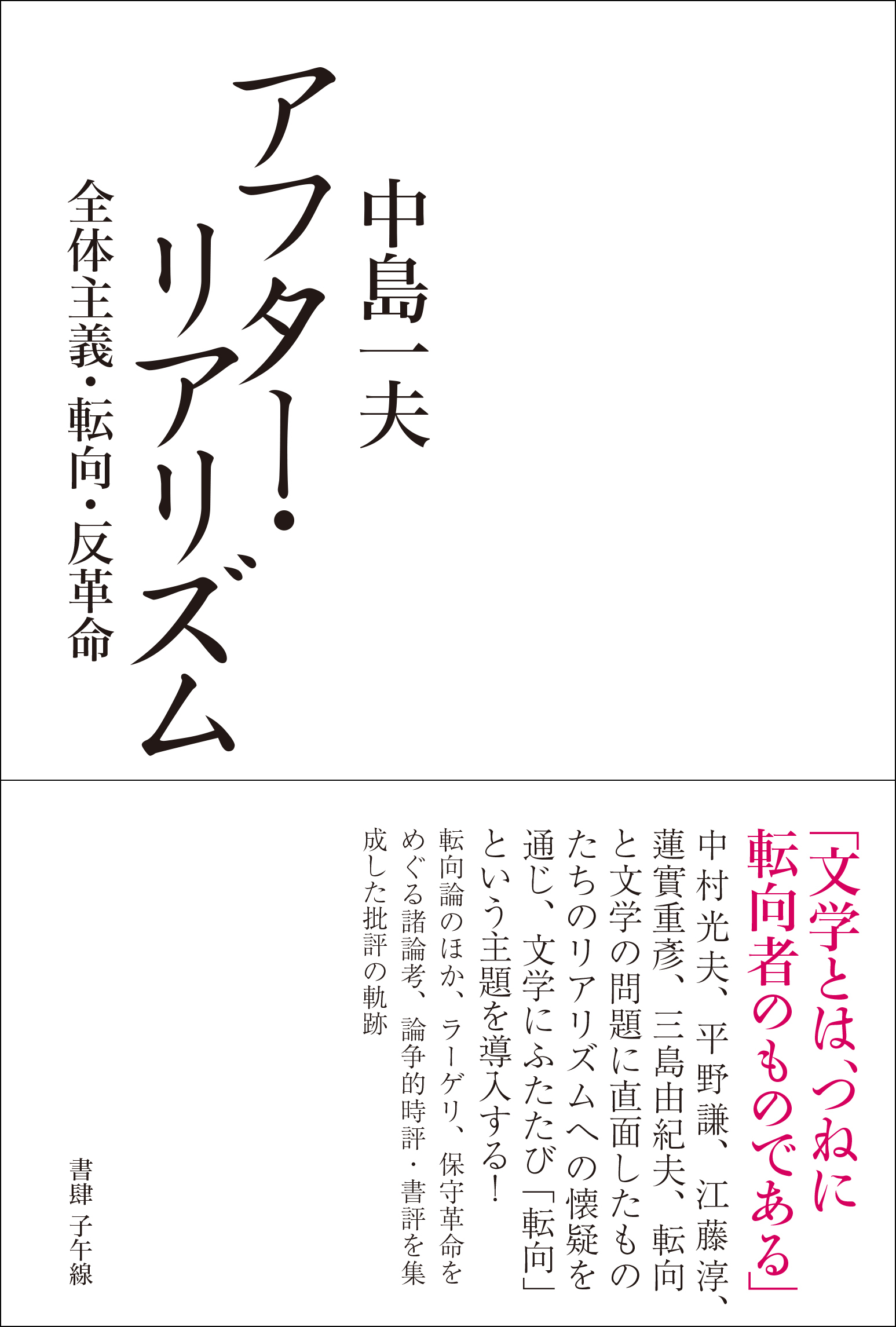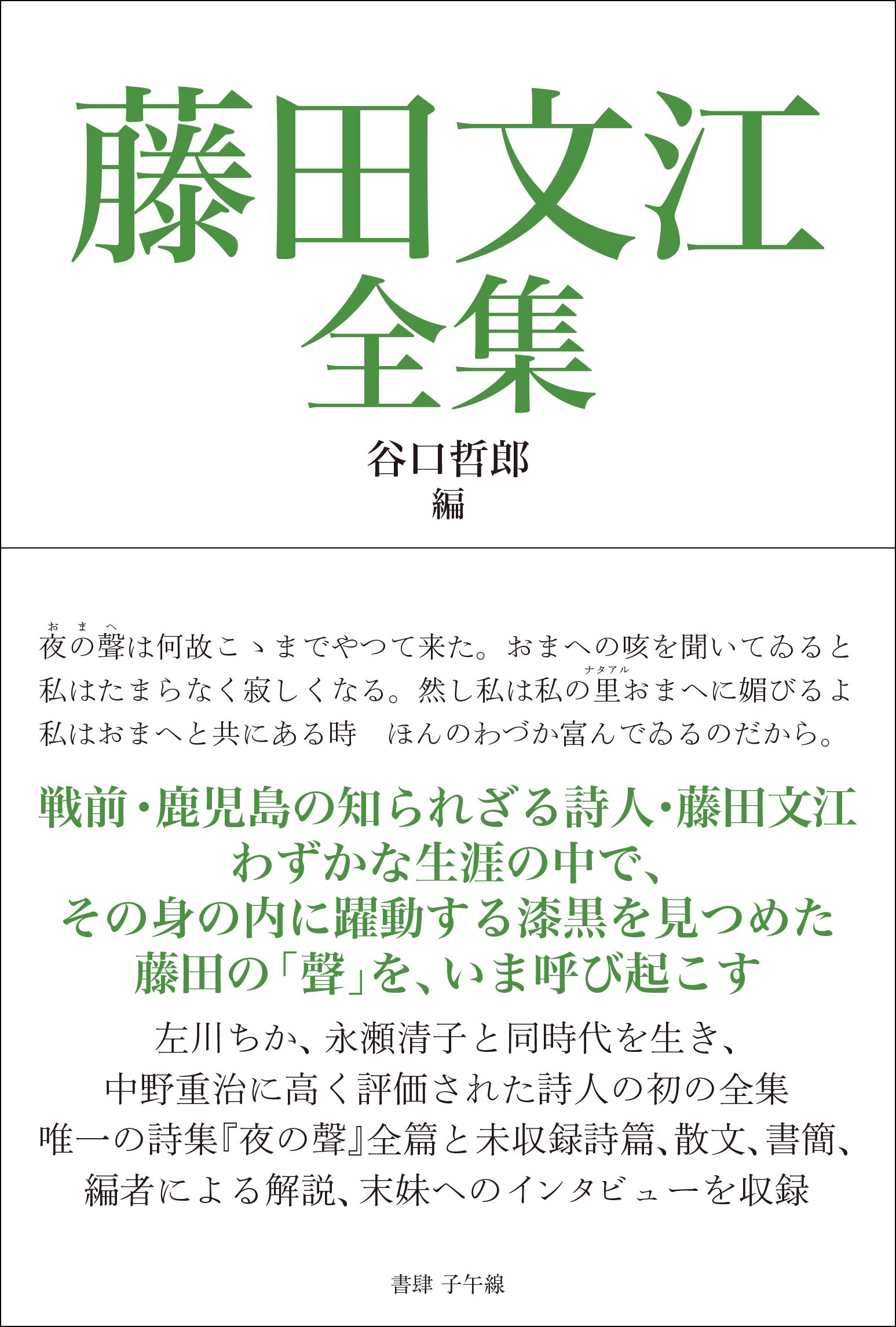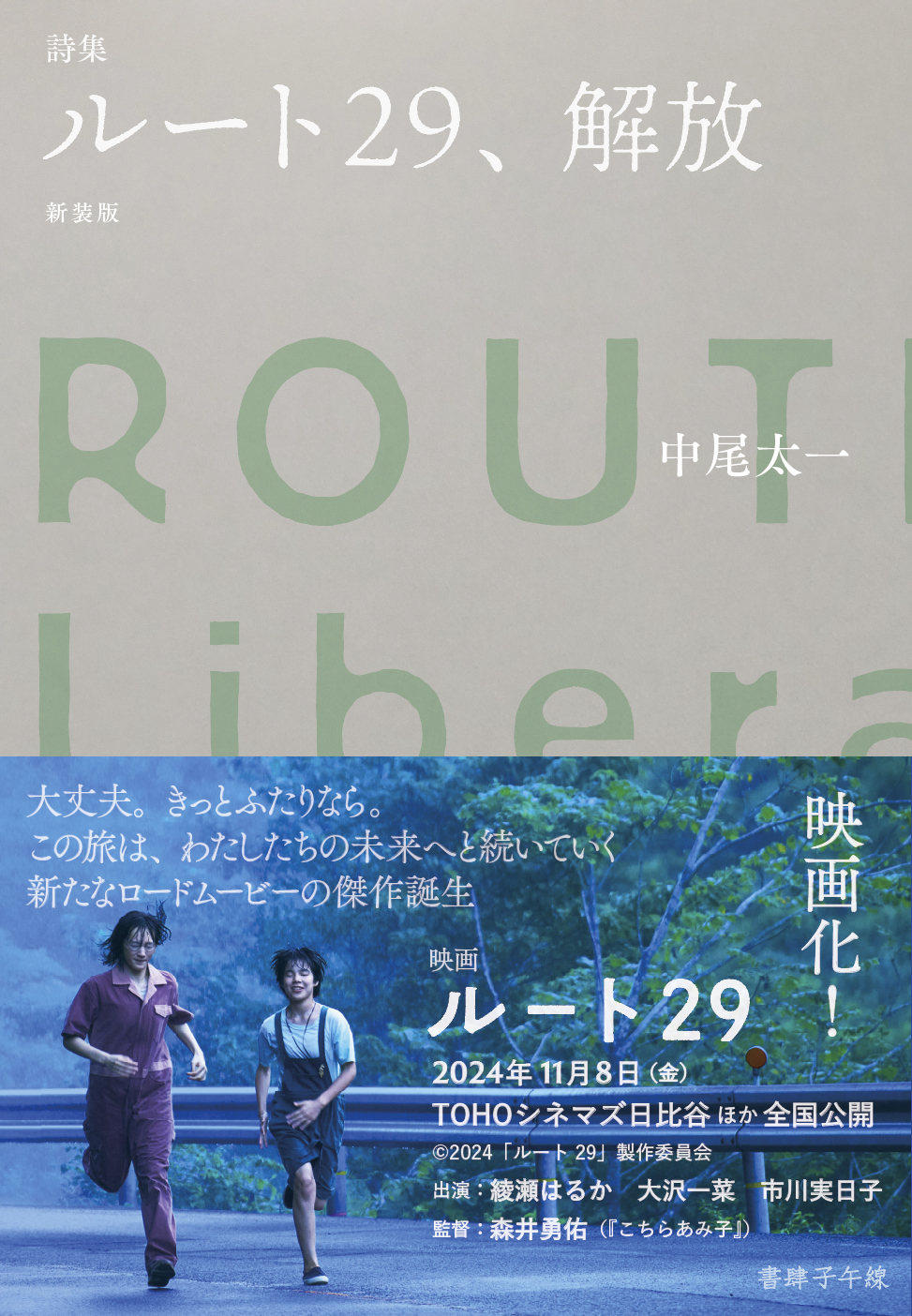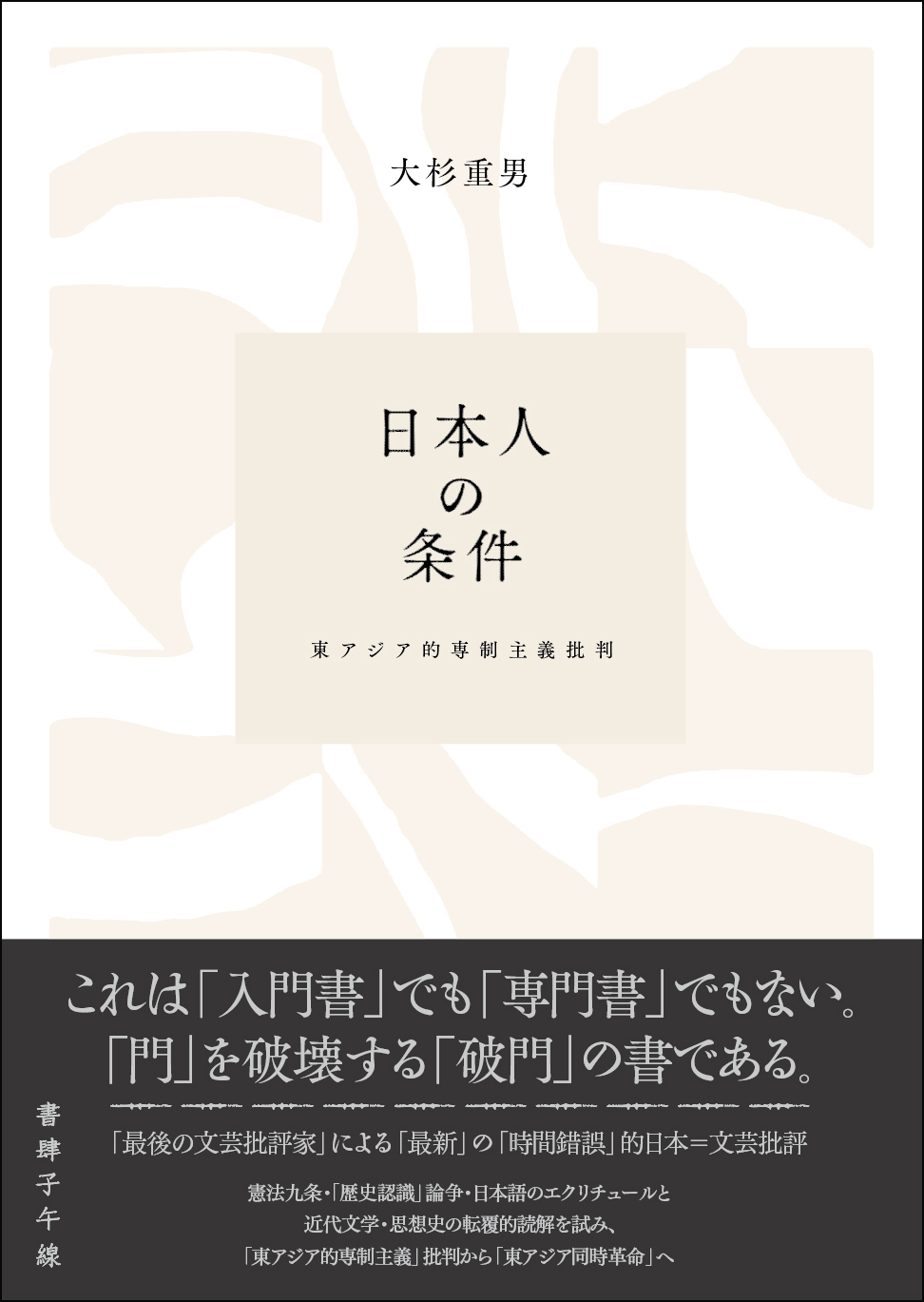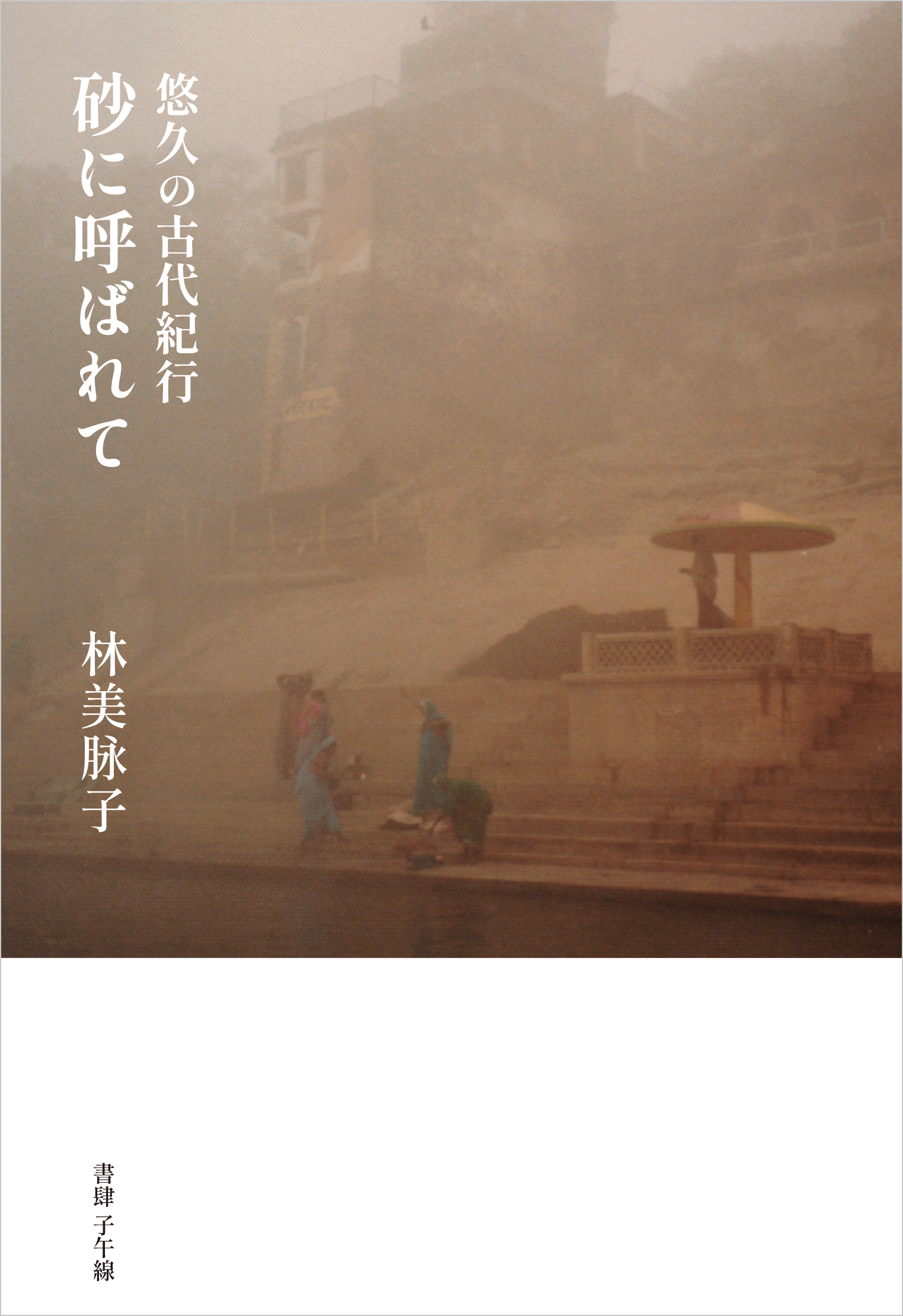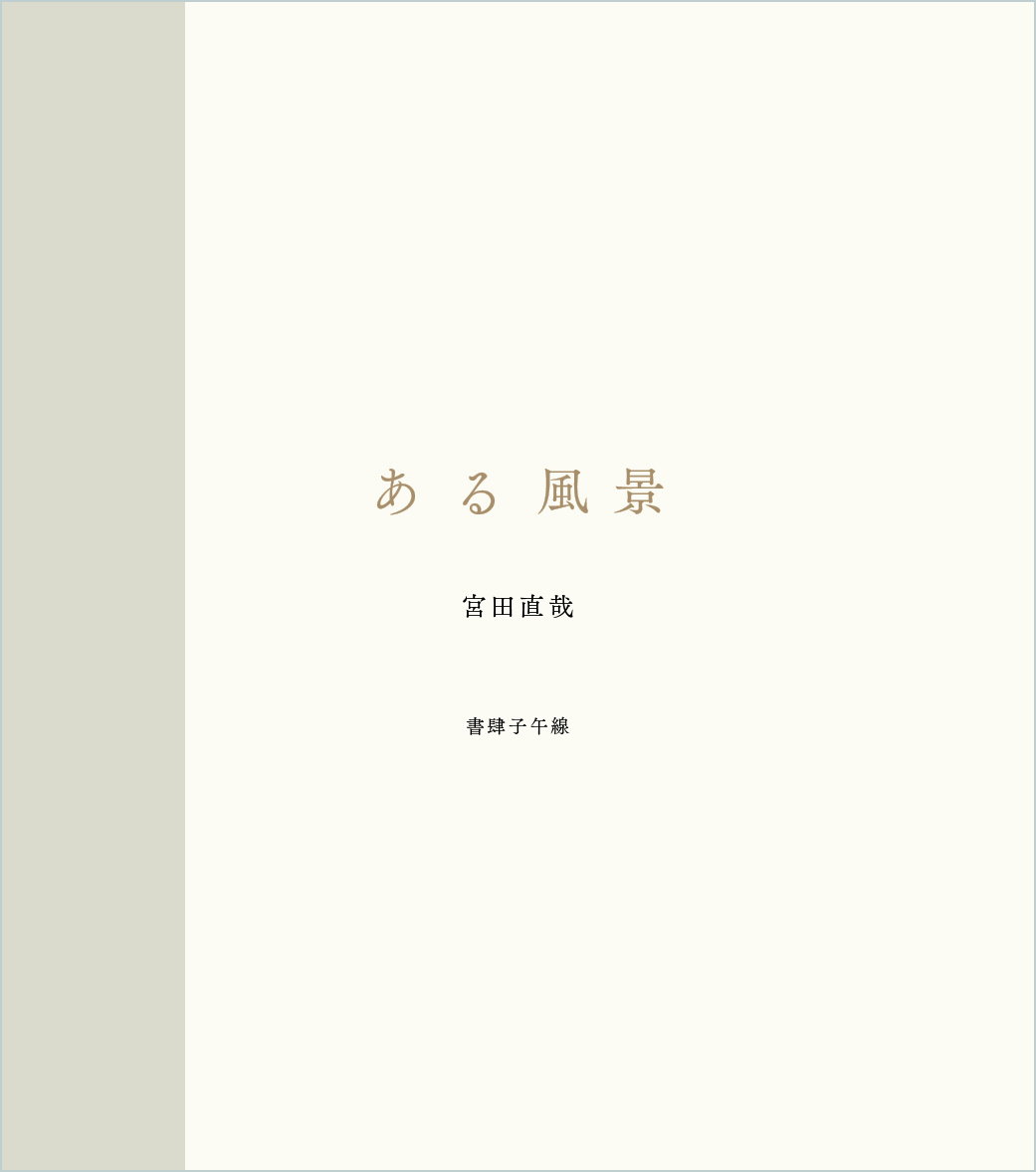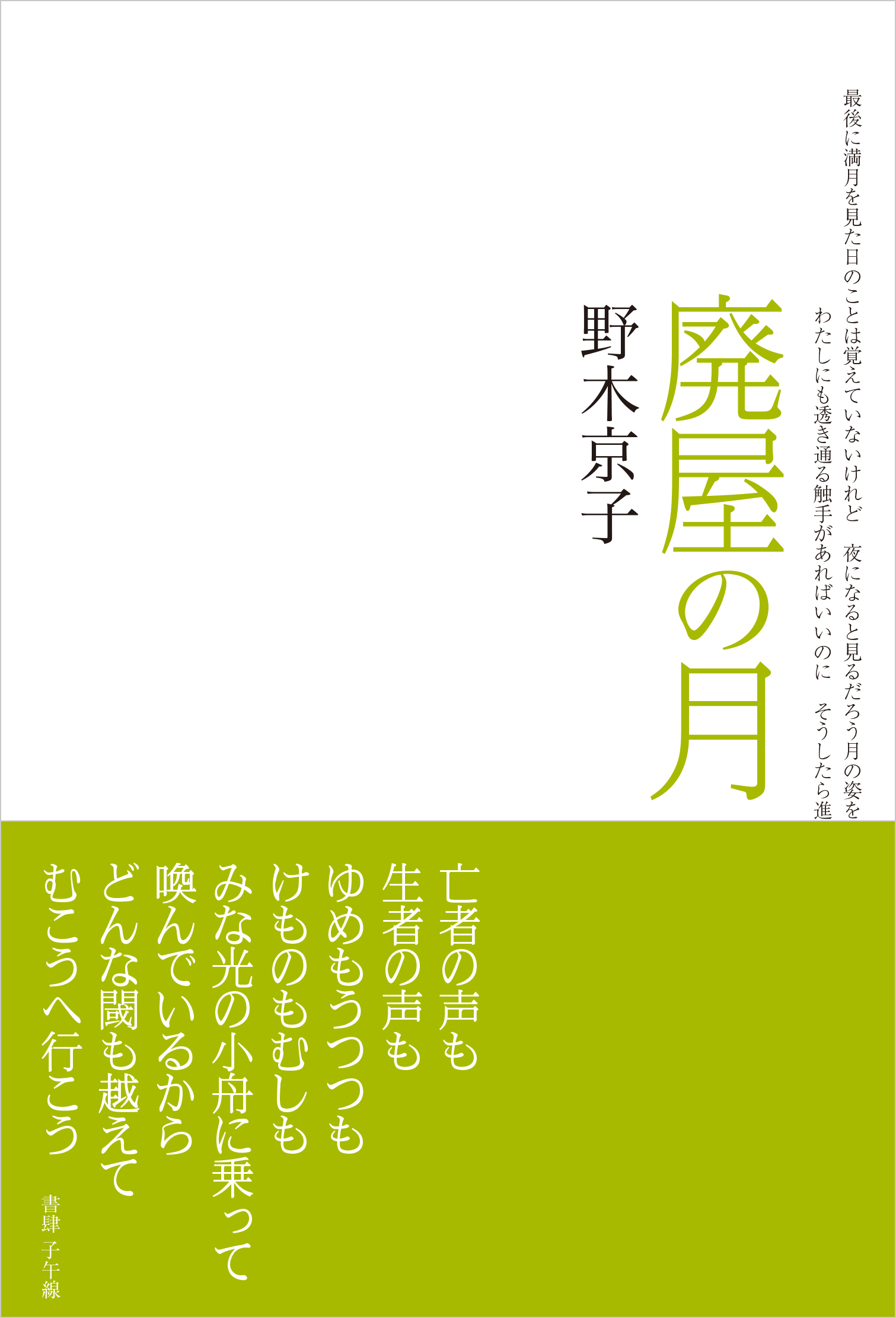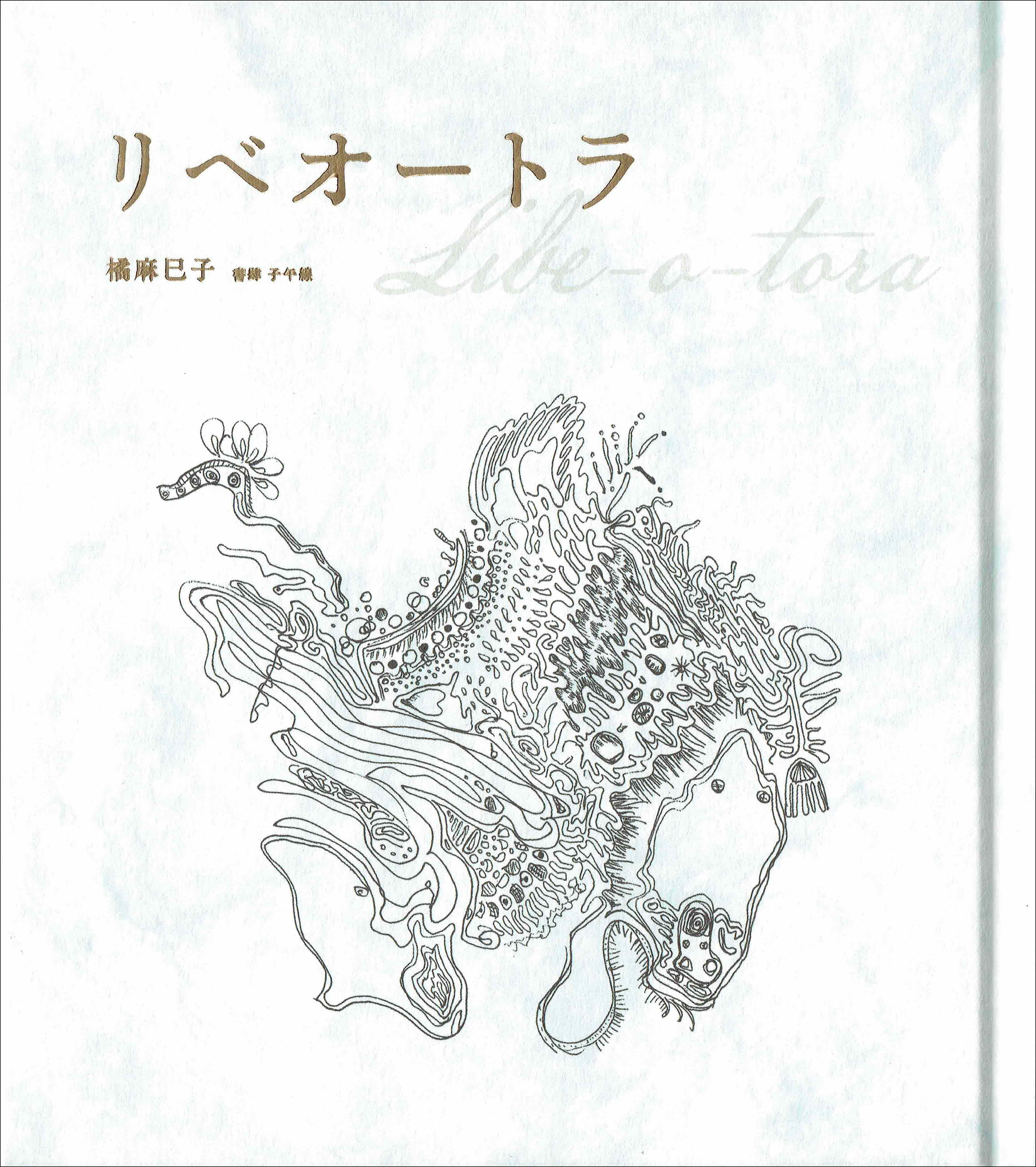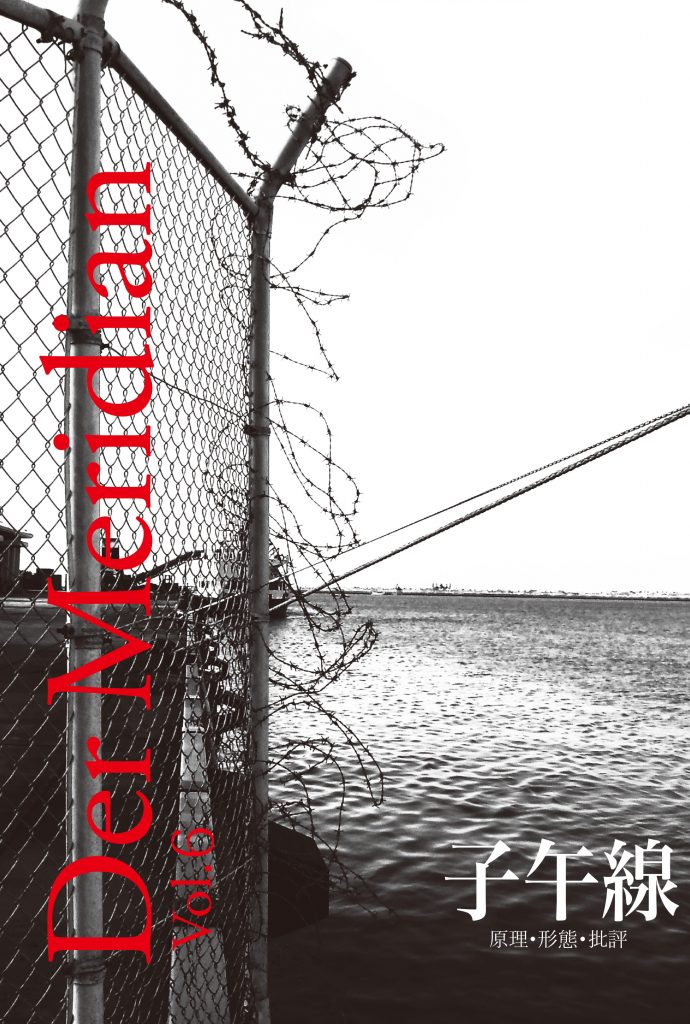『遺棄されたものたちのドローイング』
A5変形/116頁/2400円+税
社会によって遺棄された汚点、擦れた絵の具、折れた鉛筆の芯、チャコールの屑。線にもなりきれず、ただ不快として投げられた痕跡。その粗野のなかに潜む慎重な粗暴さ、あるいは、投げやりな囁き声をどうか聴き取ってほしい。
強烈な印象をもたらした第一詩集『零時のラッパをぶっ放せ』から8年、第二詩集ついに刊行!
装幀=清岡秀哉
春はリハーサルで終わった、夏はバーモントが攻めてくるだろう、痣だらけの部屋がソフトフォーカスに燃える、寝癖がますますひどくて、さよなら、時候の挨拶よ、「深夜のカフェインから始まるぼくらの蜂起」のために、茎燃ゆ、茎燃ゆ、ってはしゃぐなよ、隙間という隙間に錯乱を産み付けて、これはチャンスなんだろ、目脂が青く発光するのはチャンスなんだろ
(「ビジョンメガネ」より)
宮田直哉さんの詩集『ある風景』が第38回福田正夫賞を受賞!
宮田直哉さんの詩集『ある風景』が第38回福田正夫賞を受賞しました。
けれども私は待ち望んでいるのかもしれなかった。
目の前の風景が白く永遠と広がってゆく中で、
かつて互いのまぶたの上をかすめていたほのかな明かりと、
互いに感じあっていた微かな体温とが、
忘れ去られ、忘れ果てることを。
(「ある愛の風景」より)

『ある風景』
A5変形・上製/96頁/2400円+税
【新刊】福島直哉詩集『星の身体』を刊行しました。

『星の身体』
A5変形・上製(コデックス装 ドイツ装)/88頁/2400円+税
かさなりあうことのないわたしとあなたの瞳に映る記憶の故郷、彼方の岸辺。
涙を失くし、季節を失くし身体を失くしても、生まれくる無名のまたたきが次々にこぼれ落ちる。
待望の福島直哉第二詩集ついに刊行。深き抒情の森へ!
装幀=稲川方人
からだをなくして
それでも生きているさびしさをいのちと呼んで
わたしはもう二度と
誰かに会うことはなくなって
そのことに少しほっとしながら
溜息をこぼすようにそっと空を見上げて
ひかりとかげが一つの音のように
雲の中を流れてゆくあいだ
わたしはこえやことばを使うことに
激しくかなしみながら
そこで流れてゆく多くの景色を
故郷のように眺めている
(「椿の葉は鉛色の光を含み」より)
野木京子さんが詩集『廃屋の月』により第75回芸術選奨文部科学大臣賞を受賞!
野木京子さんが詩集『廃屋の月』の成果により第75回芸術選奨文部科学大臣賞を受賞されました。
空の河原かどこかで逢ったことのある
小さな子が部屋の隅から出てきて言った
ゆっくりと回転しながら
この世に現れ出たのだから
立ち去るときもきっと
見えない姿のまま
ゆるやかに回転して
戻っていくはず
そのとき真新しい風を頰に浴び
初めての色彩の景色を見るから
楽しみにしているとよいよ
と
(「空の河原」より)
水面に落ち込んだかつての月明かり、今は亡き人が昔飼っていた犬の鳴き声、夢うつつの気水域に立ち現れるさざなみのような声や断片を拾い集めるように書き継がれた32篇。詩人・野木京子、第6詩集。
装幀=稲川方人

『廃屋の月』
四六判・並製/120頁/2200円+税
3/3(月)19時〜、綿野恵太さんのシラス配信に大杉重男さんゲスト出演
3/3(月)19時からの綿野恵太さんのシラス配信「綿野恵太の失われた批評を求めて」のゲストとして大杉重男さんが主演します。
『日本人の条件 東アジア的専制主義批判』の刊行を記念しての配信です。
詳細については下記の配信サイトをご覧ください。
【ゲスト回】「最後の文芸批評家」が語る『批評の歩き方』『重力』そして『日本人の条件』
3月3日(月)19時より
https://shirasu.io/t/edoyaneko800/c/edoyaneko800/p/20250226095916?utm_source=twitter&utm_medium=organic&utm_campaign=share
ぜひご視聴ください。
冨岡悦子詩集『斐伊川相聞』第58回日本詩人クラブ賞受賞!
冨岡悦子さんの詩集『斐伊川相聞』が第58回日本詩人クラブ賞を受賞しました。
八雲たつ地は きょうは雨降り。出雲空港に降り立ったひとつの意志が時を重ねたみずからの生の消息を川の
蛇行に沿ってさまよう父に告げる。
小熊秀雄賞・小野十三郎賞受賞の『反暴力考』から4年、冨岡悦子新詩集。
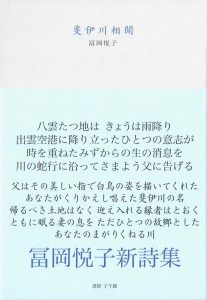
『斐伊川相聞』
四六判・上製(コデックス装 ドイツ装)/80頁/2400円+税
野木京子詩集『廃屋の月』第3回西脇順三郎賞受賞!
野木京子さんの詩集『廃屋の月』が第3回西脇順三郎賞を受賞しました。
最後に満月を見た日のことは覚えていないけれど
夜になると見るだろう月の姿を昼のうちに思い描くことはできる
わたしにも透き通る触手があればいいのに
そうしたら進む道などは光の方向でしかなくなるから
水面に落ち込んだかつての月明かり、今は亡き人が昔飼っていた犬の鳴き声、夢うつつの気水域に立ち現れるさざなみのような声や断片を拾い集めるように書き継がれた32篇。詩人・野木京子、第6詩集。
装幀=稲川方人

『廃屋の月』
四六判・並製/120頁/2200円+税
【新刊】蜆シモーヌ詩集『uta こめでぃあ uta』を刊行しました。

『uta こめでぃあ uta』
戦争、信仰、たべもの、愛、存在、涙、運命、恍惚…
オーラルにもテクスチュアルにも伸縮する言葉の群れが世界をユーモラスにうたい照らしだす
コラージュ詩から言語芸術論詩まで
複色に光る詩語たちの行進!蜆シモーヌ第三詩集
じゃ、なにか
人生は
空耳なのか。と、鼻をつまむと
そりゃー
地獄だろ、人生は。と、人生がいう
(「ランチもっと、う。まうまなランチを。地獄で」)
【新刊】中島一夫『アフター・リアリズム 全体主義・転向・反革命』を刊行しました。

『アフター・リアリズム 全体主義・転向・反革命』
文学とは、つねに転向者のものである
中村光夫、平野謙、江藤淳、蓮實重彦、三島由紀夫、転向と文学の問題に直面したものたちのリアリズムへの懐疑を通じ、文学にふたたび「転向」という主題を導入する!
転向論のほか、ラーゲリ、保守革命をめぐる諸論考、論争的時評・書評を集成した批評の軌跡。
装幀=稲川方人
私は「私」という言葉に「帰属」しない「残滓」にしかいない。それは「失われた=残滓」としての「ラザロ」だ。「探求としての文学の言語」は、言葉によって死んだ「ラザロ」を蘇らせ再現するのではなく、いかに墓の「ラザロ」、失われた「ラザロ」を求めるか、なのだ。いくら転倒して見えようとも、この逆説にしか文学の真実はない。究極、文学は、ラザロを蘇らせる者と、失われたラザロを求める者とのたたかいである。本当の文学論争はそこにしかない。
(「はじめに アフター・リアリズム、あるいは失われたラザロについて」より)
【新刊】『藤田文江全集』を刊行しました。
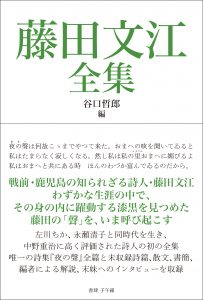
『藤田文江全集』
戦前・鹿児島の知られざる詩人・藤田文江。
わずかな生涯の中で、その身の内に躍動する漆黒を見つめた藤田の「聲」を、いま呼び起こす。
左川ちか、永瀬清子と同時代を生き、中野重治に高く評価された詩人の初の全集。
唯一の詩集『夜の聲』全篇と未収録詩篇、散文、書簡、編者による解説、妹・林山鈴子氏へのインタビューを収録。
編者=谷口哲郎/装幀=稲川方人
夜の聲は何故こゝまでやつて来た。
おまへの咳を聞いてゐると
私はたまらなく寂しくなる。
然し私は私の里おまへに媚びるよ
私はおまへと共にある時
ほんのわづか富んでゐるのだから。
(『夜の聲』より)
四六判・上製/460頁/3000円+税